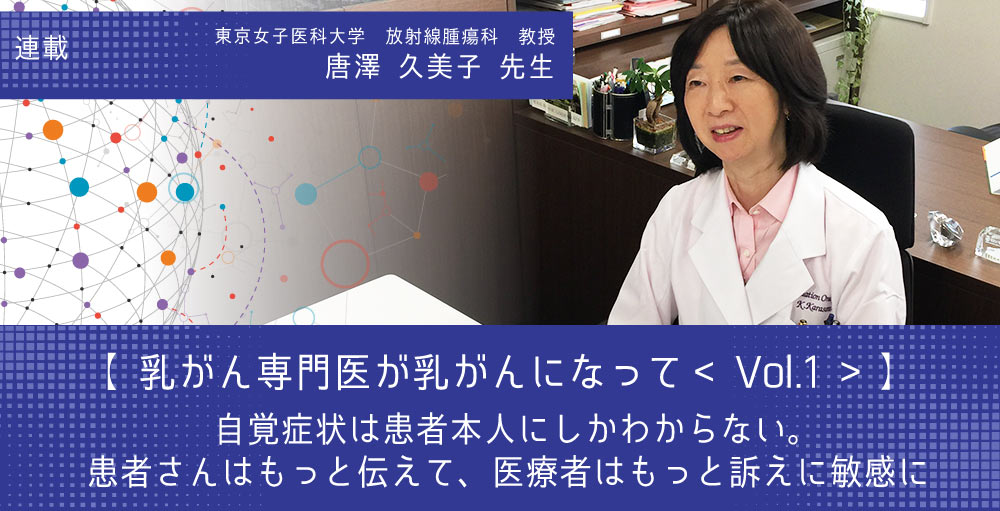数か月前に自ら乳がんを見つけ、現在、治療を続けている東京女子医科大学 放射線腫瘍科 教授の唐澤久美子さん。乳がん専門医が乳がんになって、どのように治療を選び、どんなことを感じたのかを2回に分けて伺います。
目次
自己検診によって乳がんと確信
唐澤さんが自分の乳がんを見つけたのは、ある日曜日の夜、久しぶりにのんびりと入浴し、自己検診をしていたときでした。「右内側の上部にしこりを感じました。えっ、と思って乳房と腋窩をくまなく触診し、一瞬にして“乳がん、転移はなし”と自己診断しました」。
そして、お風呂から上がってすぐに勤務する大学の乳腺外科医3人に「先ほど腫瘤を触知し、乳がんと考えられるので明日検査してほしい」とメールを送りました。
翌月曜日にマンモグラフィーと超音波検査、火曜日にMRI(核磁気共鳴画像)検査、水曜日に組織生検をして、金曜には乳がんの病理診断がつきました。土曜日にはPET/CT検査を行って遠隔転移がないことも確定しました。
唐澤さんは、乳がんになったこと自体には衝撃を受けなかったといいます。「私ががん専門医になったのは、がんは現代医学が最も克服すべき病気であると考えていたのと、家族や親戚にがんになる人がとても多く、自分も必ずがんになるだろうと思っていたからです。58歳まで発症しなかったのはむしろ遅かったくらいです。そういう意味では予定通りでした」。
病院や治療法を決めるにあたり、唐澤さんは大学の同僚以外にも親しい乳腺専門医に電話やメールで相談しました。「自分の勤務先や非常に親しい医師ではお互いに気を遣うので、信頼できる、しかも友人ではない方を主治医に選びました」。
乳がんの治療には手術、薬物療法、放射線療法があり、がんの大きさや広がり、がん細胞のタイプによって治療法が異なります。がん細胞のタイプは生検や手術によって採取した組織を調べて決められます。唐澤さんの乳がんは、ホルモン剤と抗がん剤の両方を使うことが推奨される「ルミナルB」(エストロゲン受容体が陽性で、HER2タンパクの過剰発現やHER2遺伝子の増幅がなく、乳がん細胞の増殖力を示すKi-67が高値)というサブタイプでした。
「乳がんになった身内が3人いて、3人ともホルモン剤だけで良いルミナルAタイプだったので、私だけ抗がん剤で治療することになったのは多少ショックでした。また、身内に乳がんが多いと遺伝性乳がんの可能性も疑われるため、その検査も行いましたが、陰性でした」。
そして、抗がん剤を手術の前に行う術前化学療法を受けて乳がんを縮小させてから乳房温存手術と放射線療法を行い、ホルモン剤を5年間内服するという治療の計画を立てました。
薬に弱い体質で副作用に苦しんだ
こうして、抗がん剤による術前化学療法が開始されましたが、唐澤さんはもともと薬の作用や副作用が出やすい体質でした。「例えばアレルギーを抑える抗ヒスタミン剤を飲むと強い眠気に襲われ、鎮痛剤や抗生物質では胃潰瘍を起こします。吐き気止めでは体のこわばりを起こし、CT検査のヨード造影剤にもアレルギーがあります。ですので、抗がん剤や支持療法の薬の副作用が出ることが予測されました」。
唐澤さんが使用した抗がん剤のパクリタキセルにはアレルギー反応の副作用がしばしばみられるため、その対策としてパクリタキセルを投与する直前に抗ヒスタミン薬とステロイド(副腎皮質ホルモン)を投与します。そのため、抗ヒスタミン薬の副作用がまず心配でした。
実際、初めて外来化学療法を受けた日は、「抗ヒスタミン薬を飲んでから30分後には立っていられないくらい体がだるくなり、パクリタキセルを点滴した後、どうにか帰り、その日は出勤できずに翌朝まで寝込みました。翌日は予定通りに出勤したものの、今までに経験したことのないだるさで、いつ倒れるかと思いましたが、立食の会合もどうにか乗り切りました」と唐澤さんは振り返ります。
病院での診療、大学教員や学会役員としての仕事などがぎっしりと詰まっている中、外来化学療法を続けましたが、まず薬疹やしびれが出てきました。「薬疹は顔を除いて全身に広がり、かゆみと体のだるさが辛かったですね。しかし、見た目は普通ですし、普段通り勤務していました」。
皮膚科を受診したところ、「抗がん剤が原因の薬疹であるのはほぼ間違いありませんが、もう1回受けてみないと確定診断はできませんね」と言われました。翌週に2回目のパクリタキセルを受けると薬疹はさらにひどくなり、手足のしびれも強くなってきて、抗がん剤をドセタキセルに変えることになりました。
ドセタキセルの初回投与日は医師国家試験の結果の発表日でした。国家試験を受験した6年生の担任だった唐澤さんは、残念ながら合格できなかった8人の学生に夜中までかかって手書きで励ましの手紙を書きました。
「手がしびれて頭がぼーっとしていて、これはきつかったですね。もちろん学生たちには私のがんの話はしていません。学生部長から後で学生が手紙を読んで泣いていたと聞き、私の気持ちは届いたようで、ホッとしました」。
その晩は、ドセタキセルの神経障害で全身がしびれて痛みが強く、眠れませんでした。「このまま抗がん剤の治療を続けていたら、どうなるんだろう、死ぬかもしれないと暗闇の中で恐怖を感じました」と唐澤さんは語りました。
翌日も体調は回復しませんでしたが、仙台での会合に行くかどうか散々迷ったあげく、出かけました。重要な会合で、自分が欠席すると迷惑がかかると思ったからです。
「家から駅までタクシー、新幹線はグランクラスで爆睡、仙台駅から会議場までもタクシーで移動し、会合だけ出て、逆コースを辿って帰ってきました。元来、負けず嫌いな性格ですので、何とか普通に見えるようにがんばりました」。
唐澤さんが予想外だったのが、翌日に始まった激しい下痢でした。2日間は投薬で症状を抑えて普段通りに診察業務などを行いましたが、その後は腹痛がひどくなり、欠勤。そして、腹痛がさらにひどくなり、週末に入院しました。
パクリタキセルの副作用は骨髄抑制、脱毛、アレルギー反応、しびれのような末梢神経障害、ドセタキセルの副作用は骨髄抑制、脱毛、浮腫、発疹、アレルギー反応などです。
「私はかつてパクリタキセルやドセタキセルの臨床試験を手がけたことがあり、これらの薬の効果や副作用はある程度はわかっているつもりでした。ところが、自分自身が使ってみると、これまで担当した患者さんでは経験したことがないようなひどい副作用が起こりました。特にここまでひどい下痢は経験したことがありませんでした」と唐澤さんは話します。
こうした経験から、標準治療とされている薬物療法は副作用の出方に大きな差があり、誰でも同じように受けられる治療ではないということをあらためて実感しました。
そして、効果的で安全な薬物療法を実施するためには、「一部の患者さんについては標準を踏まえた上で、患者さんの特性や状態に合わせてがんの薬物療法専門医(腫瘍内科医)が薬剤を調整するなど、きめ細かい配慮が必要になりますね」と語ります。
腹痛の原因を探るための血液検査では、支持療法としてステロイドを飲んでいたために炎症反応が見られませんでした。しかし、「骨髄抑制が起こって、好中球が304まで落ちていました。さらに腹部のCT検査で痛い場所に一致して憩室(大腸の壁が外側に膨らむ状態)がいくつも映っていたので、憩室炎の状態になっていると判断しました。もうこれ以上、継続して抗がん剤を使うのは無理だと感じました」。
入院中に看護師の応対や言葉遣いにストレスを感じた
唐澤さんが緊急入院したのは乳腺科の病棟ではなく、混合病棟の少し高額な個室でした。そこしか空いていなかったからです。多くの科のさまざまな病気の患者さんが入院する混合病棟ということもあって、病棟の看護師はがんや薬について詳しいわけではありませんでした。
そうした看護師から伝えられる乳がんの情報が古かったり、腸のけいれんによる激しい痛みに一般的な消炎鎮痛薬を薦められたりしたことなどは、医師であり、がんの専門医である唐澤さんにはストレスになったといいます。
「ラウンドのときには一応、“いかがですか”と聞かれますが、点滴の落ち具合のチェックに来ているだけのように思えたのも残念でした。私のおなかに手を当てて看てくれた看護師さんは一人だけでした。この人は看護ができていると思いましたね」。
また、一部の看護師の話し方が耳障りでした。ある看護師に「何かお仕事をされているんですかぁ」「あ、医者ですか、その歳でまだお仕事されているんですか」などと言われて驚いたともいいます。
「病院では“患者”という立場で括られてしまいますが、それぞれに社会的背景を持っています。病棟では入院時に書類を書かせてその患者さんの職業などの情報を入手しているのですから、もっと個々の患者さんの背景を踏まえた上で応対してほしいと思いました」。
唐澤さんがこの術前化学療法の治療や副作用での経験から学んだのは、痛みや違和感、具合の悪さは自分にしかわからない、だから、患者さんは自覚症状を必ず早めに詳しく医療者に伝えるべきだということ、また、医療者は患者さんの言葉にもっと耳を傾け、対応を真剣に考えるべきだということです。
「そうでないと患者さんの具合がさらに悪くなったり、医療者不信になったりしていきます。医療者はもっと患者さんに学ばなければいけないですね」。
唐澤さんは5日間入院して腹痛が軽快し、少し食べられるようになって、退院しました。薬疹は少し残っていましたが、ステロイドなどの支持療法の薬は少しずつ減らし、飲まないようになりました。
第2回記事:【第2回】~乳がん専門医が乳がんになって~ 東京女子医科大学放射線腫瘍科教授 唐澤久美子さん「がんの治療選択で最も大事なのは 患者さん自身の「人生の質」を守ること」