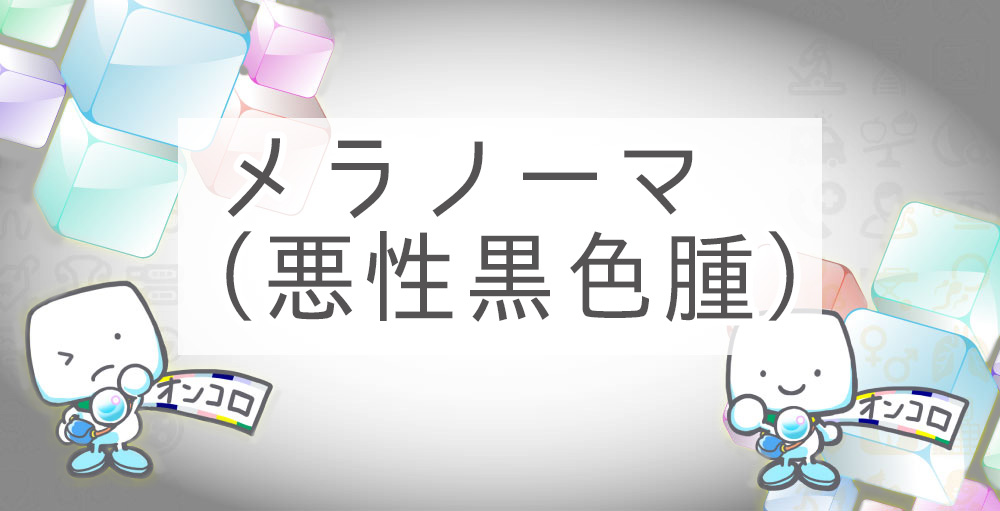目次
メラノーマ(悪性黒色腫)とは
皮膚悪性腫瘍の1つであるメラノーマは、皮膚のメラニン色素を産生するメラノサイト、またはホクロの細胞である母斑細胞が悪性化した腫瘍です。発生原因や病型、発生部位、患者数などは、人種による疫学的な差が大きいのが特徴です。
患者数の動向
メラノーマは罹患率が10万人あたり6人未満と定められている希少がんに該当し、日本の2012年のデータでは10万人あたり1人、2015年の患者数は約3000人でした。皮膚悪性腫瘍の中でメラノーマは3番目に多く、全体の12%を占めます。性差はありませんが、高齢化に伴い罹患率は上昇しており、メラノーマによる死亡率は過去40年間でおよそ4倍に増加しました。
発生原因
メラノーマの発生原因には遺伝因子、環境因子の双方が考えられていますが、白色人種の方が有色人種より数倍多いこと、紫外線の強い地域に多いことから、白色人種とメラノーマとの間には紫外線が介在することが指摘されています。
例えば、オーストラリアの罹患率は10万人あたり35人ですが、特に紫外線が強いクイーンズランド州では10万人あたりで日本の70倍から80倍にのぼります。さらに、白色人種ではメラノーマを遺伝的に発生しやすい家系があることも示唆されています。
一方、日本人では紫外線の直接的な影響が少ない足裏や手掌、手足の爪、粘膜などに多く発生することから、環境因子としての紫外線の関与は少ないと考えられ、発生しやすい家系も明らかではありません。
早期発見の手がかり
メラノーマは、自分で見える、触れることができる場所であれば、自身で早期に発見することが可能です。形、色、大きさなどの一定の基準に照らし、通常のホクロやシミと識別することも不可能ではありません。
メラノーマを識別する病変・症状の基準は次のとおりです(ABCDEルール)。
(1)Asymmetry:左右不対称
(2)Border irregularity:辺縁不整
(3)Color:色調不均一
(4)Diameter:直径7mm以上
(5)Enlargement(Elevation):急激な増大
検査・診断
皮膚科専門医による肉眼での臨床所見、および病変を拡大して観察できるダーモスコープによる検査を経て、病変の組織診断により診断を確定します。さらに、CTやMRI、超音波検査などの画像診断により転移の有無を確認します(スライドNo.16)。
病型分類
メラノーマは主に次の4病型に分けられ、人種や年齢、発生部位、症状などの特徴が異なります。
(1)肢端黒子型黒色腫(ALM)
(2)表在拡大型黒色腫(SSM)
(3)結節型黒色腫(NM)
(4)悪性黒子型黒色腫(LMM)
日本人に最も多いのは(1)肢端黒子型黒色腫(ALM)で、2005年から2013年の調査によると、メラノーマ全体の41%を占めました。ALMは足裏や手掌にできた褐色・黒褐色のシミが次第に濃くなり、潰瘍ができたりします。
また、手足の爪にできた黒褐色の縦のスジが次第に拡大し、爪周辺の皮膚にしみ出してくることもあります。日本人患者のおよそ3分の1は足裏のALMです。日本人患者で特に注意を要するのは粘膜のメラノーマで、上記4病型には含まれないものの、全体の9%を占め、結膜や口腔内、鼻腔内、外陰部、肛門などの粘膜に発生するため発見が遅れがちになります。
一方、同じ調査での米国のALMの割合はわずか1%で、SSMが63%を占めました。SSMは白人に多い病型で、体幹や手足のホクロ細胞から発生すると考えられており、まだら状に盛り上がった輪郭不整のシミとして出現します。
病期分類
メラノーマの病期(臨床ステージ)は、がんの厚みと潰瘍の有無、リンパ節や周辺皮膚への転移の有無、および遠隔の他の臓器転移の有無に基づき、がんが表皮内にとどまっている0期から、転移がないI期(Ia、Ib)とII期(IIa、IIb、IIc)、リンパ節・周辺皮膚の転移があるIII期(IIIa、IIIb、IIIc)、遠隔転移があるIV期に分類されています。