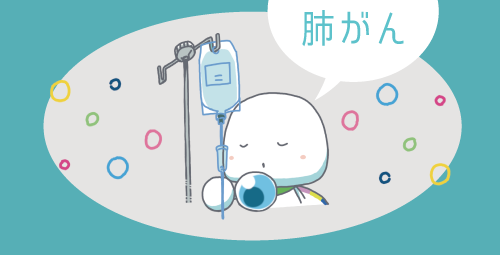目次
肺がん治療について
肺がんそのものを治療する手術や放射線療法などの局所療法と、全身に広がったがんを治療する薬物療法などの全身療法、これらを組み合わせる集学的治療に大別されます。病期と全身状態から、1人ひとりにベストな治療法が選択されます。
肺がんを治すために行われる治療には、手術、放射線療法、薬物療法 (化学療法)の3つがあります。手術、放射線療法が肺がんそのもの(病巣局所)に的を絞って行われる局所療法であるのに対して、薬物療法は肺がん(病巣)がいくつかある、あるいは肉眼的に限局しているようでも全身にがん細胞が散らばっている可能性がある場合に行われる全身療法であるという点で異なります。
このほかに、がんがもたらす症状を和らげるための治療として緩和ケアがあります。緩和ケアは「つらさを和らげる」ために施す治療であり、手の施しようがなくなった時に取り入れるものでは決してありません。早期から導入することにより、予後がよくなるという臨床試験結果もあり、診断直後から導入することが推奨されています。
これらの治療は単独で行われるだけでなく、各々の利点を利用することにより治療効果が高まることを期待して、2つ以上を組み合わせて行われることがあります(集学的治療)。その組み合わせとし
ては、局所療法と全身療法が一般的です。
たとえば、目に見えないけれど残存しているかもしれないがん細胞を根絶する目的で抗がん剤を投与する術後補助化学療法や、単独よりも併用のほうが高い効果を得られることが明らかになっている化学放射線療法です。後者には放射線療法を終えた後に化学療法を追加する逐次併用療法と、化学療法と放射線療法を同時期に始める同時併用療法があります。
ただし、集学的治療は副作用も相乗的に強まる傾向があり、化学放射線療法では同時併用が逐次併用よりも効果が高い一方、副作用が強いこともわかっています。どのように治療を行うかは、がんの組織型、病期、年齢、一般的な全身状態(パフォーマンスステータス・PS)、心臓・肺・肝臓・腎臓などの機能、ほかにかかっている病気などを考慮に入れたうえで決定されます。
非小細胞肺がんの治療
非小細胞肺がんは早期から転移しやすいわけではないものの放射線療法、薬物療法が効きにくいため、1、2期の早期の患者さんには手術を選択し、2期の方には術後補助化学療法がおこなわれる場合があります。一方、1~2期の方でも他の病気などが原因で手術ができない場合は根治目的の放射線療法あるいは放射線化学療法を使用します。
3期は、3A期などで手術での根治切除が可能な場合は手術を行う場合がありますが、原則放射線化学療法にて根治を目指すことになります。近年では、根治放射線化学療法後に、免疫チェックポイント阻害薬デュルバルマブ(商品名イミンフィジ)を地固め療法と使用することもできるようになりました。一方、3C期は放射線化学療法にて根治を目指すことが難しくなり、4期に準じた治療を行うことが多いです。
4期は、手術や放射線化学療法などで根治を目指すことが難しいため、薬物療法が中心となります。しかしながら、非小細胞肺がんの治療は、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった新しいお薬が登場したことにより、近年、少ない割合ではありますが5年を超えてがんと共生できる時代になりました。
小細胞肺がんの治療
小細胞肺がんは早期から転移しやすく、薬物療法が効きやすいため、I期を除いて手術の適応はなく、早期症例でも薬物療法を選択すべきだと考えられています。そのうえで、各病期に応じた治療法が推奨されていますが、集学的治療が進行期だけでなく、比較的早期の肺がんに対して確実に治すために試みられたり、緩和ケアが放射線療法や薬物療法と並行しながら、治療に伴う痛みや呼吸困難を取るために行われたりとバリエーションに富んでいます。
パフォーマンス・ステータス(PS)など~その他の治療決定の指標~
集学的治療は副作用も相乗的に強まる傾向があり、化学放射線療法では同時併用が逐次併用よりも効果が高い一方、副作用が強いこともわかっています。
どのように治療を行うかは、がんの組織型、病期、年齢、一般的な全身状態(パフォーマンスステータス・PS)、心臓・肺・肝臓・腎臓などの機能、ほかにかかっている病気などを考慮に入れたうえで決定されます。
PSからは、手術、放射線療法、薬物療法いずれも、PS 0~2までが一般的な適応とされています。実際の治療は、まず放射線療法や薬物療法への反応が異なる非小細胞肺がんと小細胞肺がんで分けられます。
重要なことは、患者さん自身が担当医と相談しながら、ときにセカンドオピニオンを利用して、自分自身の状態を理解し、納得したうえでベストな治療法を選ぶことです。