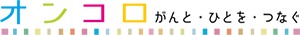目次
肝臓がん治療について
肝臓がんの治療は、病期と肝臓の障害の程度を考慮して決められます。主な治療法は、肝臓を切除する手術療法、ラジオ波の熱でがんを焼くラジオ波焼灼療法、エタノールを注入してがんを壊死させるエタノール注入療法、がんに栄養を送る血管をふさいで兵糧攻めにする肝動脈化学塞栓療法、分子標的薬などを用いた全身化学療法、重粒子線やコンピューター制御を用いた放射線療法、および肝移植です。これらの中から病期や肝臓の障害の程度などを考慮し、適切な治療が選択されます。
肝臓がんの手術(外科治療)
手術療法(肝切除術)は、肝臓がんの標準治療の1つです。肝臓がんは、肝臓を門脈の支配する区域ごとに分けて切除範囲を決める「系統的肝切除」という考えに基づき、安全に確実に切除されます。
肝切除術は、肝臓がんで最も根治性の高い治療法です。ガイドラインでは、がんの大きさはとくに問われず、「肝障害度がAかBで、がんの個数が3個まで」の肝臓がんに対して、第1選択の治療法として推奨されています。
じつは、かつての肝切除術は非常に難しくて危険な手術でした。しかし、1985年に肝臓をいくつかの区域に分けて区域ごとに切除する「系統的肝切除術」という考え方が手術療法に応用され、さまざまな技術の進歩により安全に確実にがんを切除できるようになりました。
肝臓は、中に入り込んでいる門脈が枝分かれし、それぞれの血流の範囲によって8つの区域(支配領域)に分かれています。肝臓がんは門脈の血流に乗って転移するため、がんのある門脈の支配領域を丸ごと切除すれば、再発を減らせるだろうと考え出されたのが「系統的肝切除術」です。
肝切除術では、全身麻酔をした後、みぞおちから腹部にかけてJ字に切開し、手術前にCTやMRIなどの画像検査で特定した、がんのある区域を丁寧に止血しながら切除していきます。わが国では、肝臓を1番の尾状葉、2~4番の左葉、5~8番の右葉と、8つの区域に番号をつけて分割した「クイノーの分類」を「亜区域」、右葉の後区域と前区域、左葉の内側区域と外側区域の4つに分割した「ヒーリー&シュロイの分類」を「区域」として、がんの位置や大きさ、数などに応じて使い分けながら、葉切除、区域切除、亜区域切除といった手術を行っています。
肝切除術を行うにあたり、重要なことは肝機能を維持させることです。もともと肝機能が良好であれば肝臓の再生能力は高く、手術によって小さくなった容積も2~6か月ほどで十分に再生します。そのため、肝臓を切除できる範囲は、肝障害度で決まってきます。それは、「幕内(まくうち)基準」と呼ばれるアルゴリズムに則り、腹水の有無、血清ビリルビン値、および肝機能をみるためのICG(インドシアニン・グリーン)テストから決められます。
事前にCTやMRIなどの画像から測定しておいた切除の予定範囲が幕内基準で得られた切除可能範囲に収まっているかどうかを照らし合わせ、それが収まっていれば肝切除術の対象になります。例えば、ICGが28%であれば1/6の切除が可能なので、がんが1つの亜区域(~1/6)に発症していれば亜区域切除を行えます。しかし、がんが2つの亜区域にまたがって発症していると切除可能範囲を超えた1/3の切除が必要になるため、腫瘍の周辺だけを切除する部分切除(非系統的肝切除術)、あるいは腫瘍だけをくりぬいて切除する腫瘍核出術を行います。
肝臓がんは再発しやすいため、再発時に十分な治療が行えるかどうかで生命予後が決まります。肝切除術の適応をきちんと選べば、再発時に2~4割は再手術が可能です。なかには4~6回、肝切除術を繰り返し、長期間普通に生活する患者さんもいます。
なお、肝切除術は開腹手術以外に、腹部に複数の小さな穴を開け、そこから内視鏡や器具を挿入して手術を行う腹腔鏡下手術という方法があります。一部の患者さんに適応可能ですので、希望する場合は担当医にお尋ねください。
手術経過について
手術の翌日から歩行を開始し、退院後は普通に生活してかまいません。肝切除後の5年再発率は70%程度と高いため、再発がんの早期発見をめざし、超高危険群として定期的な検査を受けることが大切です。
手術直後はICU(集中治療室)で管理されますが、翌日には一般病棟に戻り、歩行を開始します。術後3日目まで背中に入れた管から痛み止め(硬膜外麻酔)を注入するほか、必要に応じて鎮痛剤を追加するので、痛みで苦しむことはそれほどありません。ただし、十分に痛みがとれず、動けないときは担当医や看護師などに相談してください。
安静にし過ぎていると痰などを誤嚥し、肺炎を起こすこともあるので、痛みをとり、早期に離床することが大切だからです。また、胃などの手術と違い、肝切除術では手術の翌日から食事ができます。合併症などが起こらず経過が順調で、肝機能の状態に問題がなければ術後10日~2週間で退院となります。
現在は安全に手術が行えるようになっているので、術後の合併症は大きく減っています。それでも、後出血、胆汁漏、腹腔内膿瘍、皮下膿瘍、腹水・胸水などの合併症がまれに起こることがあります。術後にじわじわとにじむように出血する後出血は、1年に1例程度の頻度で起こり、止血手術が必要になります。
切除した面から胆汁が漏れる胆汁漏は6~10%と比較的多くみられ、2~3日様子をみて止まる気配がなければ胆汁が漏れている部分を再縫合したり、内視鏡を用いてチューブを入れ胆汁を抜いたりします。切った部分に膿がたまる腹腔内膿瘍や皮下膿瘍では膿を管で抜いたり、腹水や胸水がたまったときは水を針で抜いたりします。このような合併症が起こった場合は、再手術や処置などのために入院期間が延びることがあります。
退院後、傷さえ治れば、仕事も遊びも、食事も運動も、ほぼ今までどおりの生活を送ることができます。手術でいったん低下した肝機能も、2~6か月ほど経てば元に戻ります。ただし、手術でがんを取り除いたとはいえ、肝臓がんを発生させる素地となる慢性肝炎や肝硬変は治っていません。
それらの治療を継続するとともに、再発する可能性の高い肝臓がんを早期に発見するために、超高危険群として定期的に肝臓がんの検査を行う必要があります。すなわち、3~4か月ごとに超音波検査、腫瘍マーカーの測定を、6~12か月ごとにCT、MRI検査を行います。一般に、術後2~3か月までは月1回、以後は3か月ごとに受診し、半年目までは肝臓がんの検査とともに術後の影響(浮腫、腹水など)についても診察します。なお、受診間隔は、病理検査の結果なども考慮されるので担当医の指示に従いましょう。
肝機能の低下について
肝臓がんは根治しても、慢性肝炎や肝硬変による炎症が続いている以上、再発する可能性が極めて高いがんです。再発しても治療が受けられるように肝機能を低下させずに肝臓を守る治療や生活を続けることが大切です。
肝臓がんは根治した後も、その発症の素地となる慢性肝炎や肝硬変による炎症が持続していることから、再発する可能性が極めて高いがんです。そこで、再発予防を期待して慢性肝炎や肝硬変の原因となるアルコール性肝炎、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、B型肝炎、C型肝炎などに対する治療が引き続き行われます。具体的には、アルコール性肝炎には「禁酒」、NASHには「バランスのよい食事」と「適度な運動」、B型肝炎には薬物療法の「核酸アナログ療法」、C型肝炎も薬物療法で「インターフェロン療法」や「肝庇護(ひご)療法」が実施されます。
ただし、C型肝炎へのインターフェロン療法は治療が煩雑なうえに副作用の問題もあり、保険適用が厳密であることから肝臓がんの治療後に行われることはあまりありません。一方、B型肝炎に対する核酸アナログ療法はほぼ全例に行われます。それは根治後に核酸アナログで治療した群は、治療しなかった群に比べ、再発率はわずかに低下するにとどまったものの、生存期間には有意な延長がみられたことが明らかになっているからです。
つまり、肝臓がんで重要なことは、再発しても繰り返し治療ができるように「肝臓を守る(肝機能を低下させない)」ことです。例えば、ウルソデオキシコール酸の内服や、グリチルリチン製剤の内服・注射などで肝臓の炎症を抑えます(肝庇護療法)。
日常生活でも肝機能の維持に役立つことがあります。先に紹介した禁煙、バランスのよい食事、適度な運動のほか、肝臓に悪影響を及ぼすストレスや風邪の予防、便秘の改善、肝臓の血流をよくするための安静(食後30分間横になる)などです。また、肝硬変が進行し、むくみや腹水などがみられる時期には、おにぎり1個、カステラ1切れ、クッキー5枚と飲み物といった簡単な夜食(LES:Late Evening Snack)を取り入れるのもよいとされています。
本コンテンツは認定NPO法人キャンサーネットジャパンが2014年3月に作成した「もっと知ってほしい肝臓がんのこと」より抜粋・転記しております。