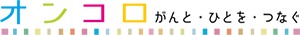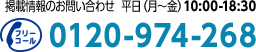目次
はじめに:がん新薬開発の最前線「第1相試験」を理解する
新しいがん治療薬の開発に不可欠な第1相試験(治験)。この記事では、その目的、臨床試験全体の中での位置づけ、具体的な参加条件、最新動向、そして患者さんやご家族が抱える疑問について、国立がん研究センターの専門家が解説したセミナー内容をもとに詳しくまとめました。抗がん剤の新薬開発の最前線である第1相試験について理解を深め、がん治療の選択肢を広げる一助となれば幸いです。
このセミナーは、がん情報サイト「オンコロ」が主催し、複数の医療研究機関・企業の協賛のもとオンラインで開催されました。司会は国立がん研究センター中央病院の山中太郎医師、講師は同センター東病院 消化管内科長の久保木恭利先生です。
講師紹介
久保木 恭利(くぼき やすとし)先生(国立がん研究センター東病院)
役職:消化管内科長(先端医療科、新薬臨床開発分野も兼務)
専門:消化器がん(胃がん、大腸がん、食道がん等)の薬物療法、新規抗がん剤の早期開発試験(第1相試験など)
資格:がん薬物療法専門医・指導医、総合内科専門医・指導医など
臨床試験(治験)とは?新薬開発のプロセス
「臨床試験(治験)」とは、新しい薬や治療法が人にとって安全で有効かを科学的に調べる研究です。抗がん剤などの新薬が世に出るまでには、以下の段階を経ます。
- 基礎研究: 新薬候補物質の探索
- 非臨床試験: 動物実験などで安全性や効果の基礎データ収集
- 臨床試験(治験): 人で安全性・有効性を確認
- 第1相試験(フェーズ1): 主に安全性と薬物動態(薬の体内での動き)、適切な投与量・投与方法を探る。少人数の患者さん(抗がん剤の場合は主にがん患者さん)が対象
- 第2相試験(フェーズ2): 有効性と安全性を評価し、最適な投与量・方法をさらに検討
- 第3相試験(フェーズ3): 既存の標準治療と比較し、有効性と安全性を最終確認。大規模に行われる
- 承認申請・審査: 国(厚生労働省)が有効性・安全性データを厳格に審査
- 承認・実用化: 承認後、保険適用などを経て一般診療で使用可能に
がん治療の最新動向と第1相試験の変化
がん治療は近年、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など新しい治療薬の登場で大きく進歩しました。これらの新しい薬剤は、第1相試験のあり方にも影響を与えています。
最新の抗がん剤の種類
分子標的治療薬(分子標的薬): がん細胞特有の分子(遺伝子変異など)を狙う薬
免疫チェックポイント阻害薬(ICI): 患者自身の免疫でがんを攻撃させる薬
抗体薬物複合体(ADC)、二重特異性抗体など: より効果を高める工夫がなされた薬
第1相試験の最近の傾向
安全性評価に加え、初期段階から有効性評価も重視されるようになりつつあります。また、早期承認制度により、有望な新薬が以前よりも早く患者さんに届くケースも見られています。
第1相試験への参加条件と流れ・注意点
第1相試験は、参加者の安全確保が最優先されるため、厳格な参加条件が設けられています。
第1相試験の主な参加条件
- 全身状態が比較的良好(Performance Statusが良い)
- 主要臓器(肝臓、腎臓など)の機能が基準内である
- 過去の治療からの回復期間が十分である
- 試験に影響を与える併用薬がない
※詳細は各治験ごとに異なります
参加後の流れ(イメージ)
- 投与量を段階的に増やしながら副作用を慎重に観察
- 定期的な検査・診察で治療効果や副作用を評価
- 血液検査などで薬物動態(薬の吸収・分布・代謝・排泄)を評価
第1相試験参加の注意点:副作用・費用・通院頻度など
- 参加条件が厳しく、希望者全員が参加できるわけではない
- 副作用が出る可能性がある(未知の副作用も含む)
- 通院頻度が多くなったり、検査が増えたりすることがある
- 遠方からの参加の場合、交通費・宿泊費などの費用負担が増える可能性がある(一部補助が出る場合もある)
- 期待される治療効果が得られない可能性もある
臨床試験(第1相試験)と民間療法の違い
科学的根拠に基づき、厳格なルールのもとで行われる臨床試験と、そうでない民間療法は明確に異なります。
| 比較項目 | 臨床試験(第1相試験含む) | 民間療法 |
|---|---|---|
| 目的 | 安全性・有効性の科学的評価、最適な用法用量の確立 | 症状改善、健康維持など(多様) |
| 根拠 | 科学的根拠に基づく | 科学的根拠が不十分な場合が多い |
| 規制 | 国の法律・指針、倫理審査委員会の承認が必要 | 規制が少ない |
| 実施体制 | 製薬企業、医療機関(専門医・スタッフ) | 個人、民間団体など |
| 費用 | 薬剤費・検査費の一部を依頼者が負担することが多い | 原則、全額自己負担 |
| 情報公開 | 結果は学会・論文で原則公開される | 限定的、客観性に欠ける場合も |
第1相試験へのアクセスを向上させる取り組み
第1相試験の情報を得たり、地理的な制約を乗り越えたりするための取り組みが進んでいます。
情報アクセス:
実施医療機関のウェブサイト(治験情報ページ)
がん情報サイト(オンコロなど)、患者会
臨床試験情報データベース(例:国立がん研究センター がん情報サービス「臨床試験を探す」)
地理的制約の緩和:
オンライン診療・相談の活用
分散型臨床試験(DCT:Decentralized Clinical Trials)の導入
病院周辺の宿泊施設利用支援
Q&A:第1相試験に関するよくある疑問と専門家の回答
セミナーで寄せられた主な質問と講師の回答です。
Q:遺伝子パネル検査で推奨薬がなくても第1相試験に参加できますか?
A(久保木先生): はい、遺伝子変異に直接対応する薬でなくても、他の作用機序を持つ標的治療薬やADCなどの第1相試験に参加できる可能性はあります。
Q:治験によって募集状況(すぐ埋まる/なかなか埋まらない)が違うのはなぜ?
A(久保木先生): 対象となるがん種や遺伝子異常の頻度、患者さんの数によります。一般的ながんや遺伝子異常を対象とする試験は早く募集が終了する傾向があります。
Q:複数のがん(重複がん)でも第1相試験に参加できますか?
A(久保木先生): 一般的には難しい場合が多いですが、がんの種類や状態など条件次第では可能です。個別の治験ごとに参加基準が異なるため、担当医への相談が不可欠です。
Q:医療者は患者さんに第1相試験の情報をどう伝えるべき?
A(久保木先生): 期待される効果だけでなく、副作用のリスク、通院頻度、費用負担の可能性、検査の詳細など、患者さんの負担となりうる点も十分に説明し、理解・納得した上で自律的に判断できるようサポートすることが重要です。
まとめ:第1相試験を理解し、がん治療の可能性を広げる
本セミナーでは、がん治療の新薬開発に不可欠な第1相試験について、その意義、最新動向、参加条件や注意点などが解説されました。がん治療は日々進歩しており、臨床試験はその進歩を支える重要なプロセスです。
患者さんは、第1相試験を含む臨床試験の特徴やリスク・ベネフィットを理解し、担当医と十分に相談した上で、ご自身にとって最適な治療選択を行うことが大切です。医療従事者は、患者さんが治験情報を正確に理解し意思決定できるよう、分かりやすい情報提供とサポートに努める必要があります。
今後、臨床試験へのアクセス環境がさらに改善され、より多くの患者さんが新しい治療の恩恵を受けられるようになることが期待されます。