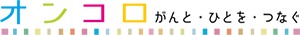第3期のがん対策推進基本計画には「初期からの緩和ケア」の重点課題として盛り込まれ、がん医療に緩和ケアが不可欠であるとの認識が広がってきた。しかし、日本全国で実際にどのような緩和ケアが提供されているか、その全体像はわかっていなかった。10月18日、東京・築地で開かれた日本がん支持療法研究グループ・J-SUPPORT研究成果報告会では、名古屋大学大学院医学系研究科基礎・臨床看護学講座准教授の佐藤一樹氏が、医療費支払いデータベースで緩和医療の質を評価した研究結果を発表した。
また、同報告会の総合討論「これからの支持療法・緩和治療・心理社会的ケアの臨床試験への期待」では、研究の企画段階から患者が参画することの意義が強調され、患者が選ぶJ-SUPPORTアワードの創設や患者会と合同のJ-SUPPORT研究全国集会の開催が提案された。
目次
5%の患者が亡くなる1カ月前に新規治療を導入
佐藤氏を中心に行った「医療ビッグデータを用いた緩和医療の質評価」(J-SUPPORT1702)では、2013~2015年の3年間に亡くなったがん患者約64万人のレセプト情報を使って、専門家による緩和ケアが実施されているかなど終末期医療の質を評価した。

佐藤 一樹 氏
レセプトは、医療機関が保険診療で行った医療行為について保険者(市区町村や健康保険組合)に毎月提出する診療報酬明細書だ。保険診療を行っている全医療機関が提出しているものなので、厚生労働省が公表しているナショナルデータベースのレセプト情報を分析することで、全国の医療機関の医療行為の実施状況が把握できる。
佐藤氏は、国際標準の指標で過剰な医療とされている「死亡前2週間の抗がん剤の継続」「死亡前1カ月の新規抗がん剤治療やICU(集中治療室)利用」の実施割合を分析した。なお、レセプト情報には、傷病名にがんとの記載がなかったり、がんと記載されていても死亡したかが明記されていなかったりする場合がある。分析した64万人は、人口動態統計と照らし合わせると、3年間にがんで亡くなった患者の約6割にあたる。
分析の結果、「死亡前1カ月のICU利用」は平均約2.5%で、心肺蘇生、人工呼吸器を使った治療は10%を超えている米国や台湾、5%のカナダよりも少なかった。「死亡前2週間の抗がん剤の継続」割合は平均約5%で、カナダ(2~3%)よりは高いが、アメリカ(10%)、台湾(30日以内で15%)より低かった。「死亡前1カ月以内の新しい抗がん剤を開始」した割合は約10%で、データは少ないがアメリカ(約5%)より高い傾向がみられた。
緩和ケアの提供率、最小県と最大県の格差7倍
この3つの過剰な医療はすべて、がん診療連携拠点病院やDPC(包括評価制度)を導入している病院で実施率が高く、患者の年齢が40歳未満に多く、血液がんの割合が高かった。亡くなる1カ月以内に新しい抗がん剤を開始した割合は血液がんに次いで肺がんや乳がんにも多く、緩和ケアチームが介入しているケースでは少ない傾向がみられた。
一方、専門的な緩和ケアを受けていた割合は緩和ケア病棟16%、緩和ケアチーム5%で、計21%だった。なお、在宅緩和ケアについては適切な項目がなかったためデータに含まれていない。「早期からの緩和ケア」は緩和ケアチームが担っていると考えられるが、「これが5%というのはやはり少ない」と佐藤氏。
専門的緩和ケアは、緩和ケアチームの存在が指定要件になっているがん診療連携拠点病院、緩和ケア病棟がある「その他の病院」での提供が多く、40歳未満や40代の若い世代と、がん種別では乳がん、子宮・卵巣がんで提供割合が高かった。
都道府県別にこの4つの指標を見ると、特に専門的な緩和ケアの提供率は最小県が5.2%、最大県が37.5%で、地域格差が大きかった。
早めのアドバンスケア・プランニングで患者のQOL下げる過剰治療削減を
「亡くなる前に抗がん剤投与やICUでの治療が必要とされている患者さんもいるかもしれませんが、一般的には、QOLが低下するとされています。終末期の積極的な治療は、早期からの緩和ケアやアドバンス・ケアプランニング(ACP、人生会議)が実施されると減るという報告もあります。医療者側と患者側の話し合いがないまま積極的な治療が行われていることもあるので、リスク因子のある患者さんに対しては、より早期から終末期に向けた話し合いが必要なのではないでしょうか」。佐藤氏はそう強調した。
Q&Aセッションでは、パンキャンジャパン理事長の眞島喜幸氏が、「私は妹を膵がんで亡くしました。妹には、新しい薬が出てきたらどんどん使おうと言っていました。家族の立場では積極的な治療の中止は言い出しにくい」と話した。佐藤氏は、「新しい分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬がどんどん出てきている中で、どこまで治療するか判断は年々難しくなっているのではないでしょうか。特に血液がんでギリギリまで抗がん剤を実施する割合がなぜ高かったかは詳細な分析が必要」と指摘した。
共同研究者で国立がん研究センター中央病院支持療法開発センター長、J-SUPPORT代表の内富庸介氏は、「血液がんの遺族の後悔やうつが一番多いことがわかっています。もちろん一番いいゴールを目指して治療するわけですが、少し早めにアドバンスケア・プランニングをし、もしものときのリハーサルを重ねるのがいい準備の一つではないでしょうか」と語った。
患者側がJ-SUPPORTアワード創設と患者団体と共催の全国集会提案
同報告会の全体のまとめとして、最後に、「これからの支持療法・緩和治療・心理社会的ケアの臨床試験への期待」をテーマに、がんサバイバー代表の3人と、J-SUPPORT代表で国立がん研究センター支持療法センター長の内富庸介氏、同センター理事長の中釜斉氏、同センター中央病院長の西田俊朗氏が総合討論を行った。
パンキャンジャパン理事長の眞島氏は、自身が昨年、中咽頭がんの薬物療法を受けた経験から次のように要望した。
「支持療法が進んだお陰で吐き気などの副作用はほとんどなかったのですが、末梢神経障害でネクタイは結べないし、物がつかみづらくすぐに落としてしまいます。がんの治療の進歩によって生存率は上がってきていますが、末梢神経障害のような副作用対策の研究も進めてほしいです」
国立がん研究センター中央病院の西田氏は、歯科医だった義兄が直腸がんになり、抗がん剤の副作用のために仕事が続けられないのが嫌で治療を中断したことに触れ、こう述べた。「義兄は患者さんの歯を治すのが生きがいで、生きがいを取られたら人生面白くないと話していました。人間いつかは死ぬので、その間をどう生きるかが大切なんじゃないでしょうか。がんの患者さんの60%以上が治るようになった中で、慢性痛をどうするか、我々医療者がつきつけられている課題です」
同センター理事長の中釜氏は、「がん対策の中でも、支持療法、緩和ケア、心理・社会的ケアの重要性、必要性が高まっています。全体として医療者がこういう分野の研究に取り組むことが必要ですし、研究の企画段階から患者さんや市民が入ってくれると視野が広がり、今回のような大きな成果を生むことが示されたと思います」と強調した。
一般社団法人CSRプロジェクト代表理事の桜井なおみ氏は、「全がん連(一般社団法人全国がん患者団体連合会)、あるいはいくつかの患者会と連携して、患者からみた一番いい研究にJ-SUPPORTペイシェントアワードを2年に1回でもいいから表彰するようにしたらどうでしょうか。将来的には寄付を集めて賞金を出せたらいいと思います」と提案。
J-SUPPORT代表の内富氏は、「倫理審査の段階から患者さんに参画してもらうのは遅すぎるので、J-SUPPORTの研究の最初の段階から入ってもらって、研究の普及と成果の実装化を図りたいと考えています。なぜかというと、歯ブラシと同じで、他人の作ったエビデンスは使わないからです。患者さんと研究者がオールジャパンで作ったエビデンスをみんなで使えるようにしていきたい」と語った。
NPO法人がんノート代表理事の岸田徹氏は、「患者体験者が支持療法などの研究をサポートができるような教育支援が必要」とコメント。桜井氏は、患者団体、アカデミアや製薬企業が協働で患者・市民参画コンソーシアム(PPI Consortium in Japan)を立ち上げ、欧州のものを参考にした患者教育プログラムを準備中であるとした。眞島氏からは、「J-SUPPORTでどの研究を進めるか決める全国大会をがん患者団体と一緒にやって、意見交換をすると、患者に役立つ研究が進むのではないか」との提案もあった。
最後に、中釜氏が「がんを病院の中で治療するだけではなくて、患者さんの社会との共生を実現できるかを考えていかなければいけないという文化がこれだけ急速に醸成したことを実感しました。今日、ディスカッションしながら改めて感じたことを、サバイバーのご意見を聞きながら、エビデンスとしていかに構築できるか大事です。我々もJ-SUPPORTの活動をますます活性化したいと思います。そのためのご支援をお願いします」と語り、報告会は閉会した。
(取材・文/医療ライター・福島安紀)
※※※J-SUPPORT報告会の記事・動画、ならびにアンケート結果はJ-SUPPORT公式Webサイトでご覧いただけます※※※
J-SUPPORT研究成果報告会レポート一覧