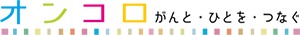第1回 がん組織の遺伝子異常と放射線の組み合わせを最適化の記事はこちらから
がんの化学療法(薬物療法)において、がん組織の遺伝子異常などのバイオマーカーを使い、薬の効果や副作用、予後を推測する個別化治療がだんだん普及してきました。一方、放射線療法についても、このようなバイオマーカーを利用して、あるいは分子イメージングを使って、治療の個別化が少しずつ始まっています。
■低酸素状態になっている部分に重点的に放射線を照射
前回は、頭頸部がんの手術で採取したがん組織に、HPV感染を示す、がん抑制タンパク質p16があれば放射線療法や化学療法が効きやすいため、放射線の治療の強度を下げることができそうだということ、また、肺がんのうちの腺がんでは、EGFR遺伝子の変異があると使われるEGFR阻害剤が放射線の効果も高めることがわかっており、化学放射線療法の効果がより高くなる可能性があることを紹介しました。
ただ、このように放射線療法の個別化の対象となるケースは、がん全体ではまだまだ少なく、また、化学療法も含めて手術や生検でがんを取れない人は現状では対象になり得ないことも事実です。
今、手術や生検といった大きな侵襲がなく、治療にも直接つながる検査法の一つとして、分子イメージングが注目されています。分子イメージングとは、生体内で起こっている生命現象を分子の動きとして画像にするもので、PET(陽電子放射断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像)、CT(コンピューター断層撮影)、SPECT(単一光子放射断層撮影)といった画像診断機器を用い、部位や映し出したい分子に応じて映りやすくするための分子プローブや放射性薬剤を組み合わせます。
がんの塊には、一人の患者さんのものであっても、さまざまな種類の細胞があり、部分によって性質が異なります。主にがん組織の中心部は低酸素状態になっており、この低酸素状態のがん組織は薬が効きにくく、その体積の割合が大きい場合には予後があまりよくないとされています。一方で、この低酸素状態のがん組織には放射線の効果が高いことも明らかになっています。
そのため、低酸素状態のがん組織が大きい場合には、放射線照射の量や回数を増やすことで治療効果が上がる可能性が高いのです。頭頸部がんや前立腺がんなどで使われる強度変調放射線療法(IMRT)は放射線の強度や方向を調整でき、低酸素状態のがん細胞の部分だけ線量を増やせます。そのため、低酸素状態のがん組織が大きい場合には、放射線照射の量や回数を増やすことで治療効果が上がる可能性が高いのです。
PET・CTやMRIといった画像診断の際に、低酸素の部分を強調して映す低酸素分子イメージングの研究が進められており、少しずつ実用化が進んでいます。
例えばドイツでは頭頸部がんの患者さんについて、PET・CTを用いて低酸素状態のがん組織の大きさを調べ、あらかじめ決めた基準よりも低酸素状態のがん組織が大きい人に対して、通常は総線量70Gy(グレイ)のところを77 Gyまで照射し、標準線量で照射した症例との違いを調べる臨床研究が始まっています。
国立がん研究センター先端医療開発センターでも皮膚がんの遺伝子をターゲットにした阻害剤を開発中で、これが分子イメージングや放射線療法と組み合わされる可能性があります。
「現在、がんの分子イメージングの中でも低酸素分子イメージングは最も臨床応用に近いところに来ていると考えられます。低酸素状態と臨床での放射線療法の照射の効果の関係が明らかになれば、追加で化学療法をするかしないかを判断する材料にもなり、また、なかなか治療しにくい転移巣への治療にも使えます。とくに手術や生検でがん組織を採取することができない患者さんには朗報です」と秋元さん。また、低酸素分子イメージングは手術後の補助化学療法の必要性の有無、再発リスクが高いかどうかの予測など、放射線療法以外にも治療や予後の予測に役に立ちます。ただし、「まだ低酸素分子イメージングの方法そのものが開発途上で、とくに低酸素状態の部分によりよく集積する分子プローブや放射性薬剤の開発が求められます」と秋元さんは語ります。
今後、遺伝子変異を描出できる薬剤が開発されれば、がん組織を採取しなくても分子イメージングで遺伝子変異の有無がわかる時代が来るかもしれません。
「患者さんの特性を反映した診断技術ができて、それに基づいて治療を組み立てられるようになれば、個別化医療が進み、患者さんに大きなメリットになるでしょう」。
なお、現在、個別化医療の元となるバイオマーカーの多くは、がんそのものの遺伝子の異常であり、患者さん自身の遺伝子の多型(バラエティ)、つまり体質を調べているわけではありません。一部のがんでは、一塩基多型(SNPs)と放射線療法の効果や副作用との関連を調べる臨床研究が始まっていますが、秋元さんは「SNPsの頻度は低いことから、その有無で治療選択を変えることができるかどうかは何万人のデータを集めて初めてわかることで、実用化はまだまだ先でしょう。何よりも先天的なものであるため、調べることによる不利益が発生する可能性があり、倫理的な問題が生じます。SNPsによる患者さんの選別、検査の費用や手間に対する社会的なコンセンサスが醸成されること、遺伝カウンセリングなどの態勢の整備が不可欠です」と話しています。
ライター 小島あゆみ