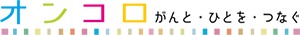目次
化学療法
乳がんの化学(薬物)療法には、抗がん剤による治療、ホルモン療法、分子標的薬による治療の3種類の方法があります。治療法は、病期、がん細胞の性質、年齢、本人の希望などに応じて決まります。
乳がんの多くは全身病で、たとえ腫瘍が小さくても、体のどこかに見えないくらい微小ながん細胞が潜んでいる危険性があり、その微小転移のリスクを消滅させるためにも化学(薬物)療法が重要な役割を果たしています。
化学(薬物)療法の目的と段階には、
①手術前に腫瘍を小さくして乳房温存手術をするため(術前(ネオアジュバント)化学(薬物)療法)
②術後に体のどこかに潜んでいるがん細胞を根絶して再発予防するため(術後薬物療法)
③最初からほかの臓器に転移があった場合や再発の治療のため
の大きく3つに分けられます。
また、乳がんの薬物療法には、抗がん剤による治療、ホルモン療法、分子標的薬による治療の3種類があります。どの薬を治療に使うか、あるいは組み合わせて使うかは、病理検査で調べたがん細胞の性質(ホルモン感受性、HER2タンパク発現の有無)と再発リスク、本人の希望などを考慮して決めます。
ホルモン療法と分子標的薬による治療は、がん自体がそれぞれの薬に反応する性質を持っていなければ効果がない治療です。自分のがんの性質と再発リスクを知ることは、治療法を選ぶうえでとても重要です。

術前に腫瘍を小さくする「術前薬物療法」
腫瘍が3センチ以上と大きいけれども、できれば乳房を温存したいという場合には、手術前に薬物療法を行います。また、炎症性乳がんの場合は、まずは薬物療法を行い、腫瘍が縮小したら手術を実施します。
抗がん剤を投与する術前化学療法の期間は3~6か月間です。HER2陽性の人はトラスツズマブを併用します。もともと手術が可能な乳がんは、化学療法を術前、術後のどちらに行っても、生存率や再発率に差はありません。術前化学療法で腫瘍が小さくなる確率は70~90%です。
術前化学療法で腫瘍が小さくなれば、乳房温存手術を受けられる可能性があり、手術による切除範囲も小さくて済みます。術前化学療法で腫瘍が消失した場合には、消失しなかったときと比べて再発リスクが約50%下がり、腫瘍と腋窩リンパ節転移の両方が消失した場合には、再発リスクが70~80%程度低くなります。術前化学療法は、抗がん剤や分子標的薬の効果をみる指標にもなっています。
現在、さまざまな臨床試験が進行中であり、今後は、その効果によって術後の治療法選択が変わってくる可能性もあります。
また、手術可能でホルモン感受性があり、すでに閉経している場合には、術前ホルモン療法を3~6か月行う場合があります。今のところ、閉経前の人の術前ホルモン療法の効果は科学的に証明されていません。ホルモン感受性ありでも、閉経前の人は、臨床試験以外では、術前ホルモン療法の対象にはならないのです。
術前薬物療法のデメリットは、がんが縮小、消失した場合には、術後に切除したものを顕微鏡でみてがんの性質を調べる確定診断が難しくなることです。術前薬物療法中に腫瘍が大きくなる人もいます。本人が、一刻も早くがんを切除したいというときには、術前薬物療法はお勧めできません。
抗がん剤による治療は
手術可能な乳がんで抗がん剤による治療が必要なのは、主に、HER2陽性乳がん、あるいは、ホルモン受容体もHER2も陰性で「トリプルネガティブ」と呼ばれる人です。ホルモン感受性ありの人はホルモン療法が主体になりますが、がんの増殖指数(Ki67)が高い、腋窩リンパ節転移4個以上、腫瘍の広がりが広範であるなど再発リスクの高い場合には抗がん剤治療(HER2陽性の人は分子標的薬も)が併用されます。
再発予防の抗がん剤治療で現在最も効果が高いとされているのは、AC療法(ドキソルビシンとシクロホスファミドを3週間に1度4回)などアンスラサイクリン系薬剤を投与したあと、タキサン系薬剤(パクリタキセルまたはドセタキセル)を追加投与する治療です。術前でも術後でも薬の内容は同じです。
ほかの臓器への遠隔転移がある場合には、副作用が強く出ないように調整しながら1つの治療法をできるだけ長く行います。
副作用が比較的少ない分子標的薬
がん細胞の生存・転移には、さまざまな分子(タンパクや遺伝子)が関わっています。この分子のみを狙い撃ちする薬が分子標的薬です。抗がん剤ががん細胞を殺すために正常細胞まで叩いてしまうのに対し、分子標的薬は、がんの増殖に関わる分子のみをターゲットに狙い撃ちするので、脱毛、吐き気といった大きな副作用が比較的少ない治療法です。
乳がんの代表的な分子標的薬はトラスツズマブ、ペルツズマブ、ラパチニブ、T-DM1(トラスツズマブと抗がん剤エムタンシンの結合薬トラスツズマブエムタンシン)といった抗HER2薬です。がんの増殖に必要な物質を取り込むHER2タンパク受容体を攻撃することで、がんの増殖を抑えます。これらの薬は、がん細胞がHER2タンパクを持っている(陽性) 人にのみ効果があります。
乳がんでHER2陽性の人は15~20%です。術前、あるいは術後にトラスツズマブをタキサン系薬剤と組み合わせて1年間投与することで、再発リスクを36%減らせます。
HER2陽性乳がんは、比較的予後の悪いがんとされてきましたが、トラスツズマブなど抗HER2薬の登場で、生存率が大きく改善しました。HER2陽性乳がんの人は、再発・転移した場合にも、抗HER2薬と抗がん剤を併用、あるいは2つの抗HER2薬を組み合わせた治療などを行います。
閉経前と後で異なるホルモン療法
乳がんには、女性ホルモンのエストロゲン(卵胞ホルモン)やプロゲステロン(黄体ホルモン)の刺激によって増殖するタイプがあります。ホルモン療法は、ホルモン感受性ありの人に対し、体内のエストロゲンを減らしたり、エストロゲンの取り込み口であるホルモン受容体に働き、エストロゲンとの結合を邪魔することでがんの増殖を抑える治療法です。
女性ホルモンをつくる機能は閉経を境に大きく変わります。そのため、ホルモン療法の内容は閉経前か閉経後かで異なります。閉経しているかが不明なときは、血液中のエストロゲンと卵胞刺激ホルモンを測って判定します。
閉経前には、エストロゲンは主に卵巣で作られます。脳の視床下部が指令を出すと、下垂体が出す「性腺刺激ホルモン」に刺激され卵巣がエストロゲンをつくるのです。閉経前のホルモン療法に用いられるLH-RHアゴニスト製剤は、下垂体から指令が出ないようにし、その結果、卵巣からのエストロゲン分泌を抑える薬です。
閉経前でホルモン感受性ありの人は、術後に、LH-RHアゴニスト製剤(卵巣機能抑制薬)を1か月または3か月に1回、2~5年間皮下注射し、抗エストロゲン薬のタモキシフェンを5年間、または10年間服用するのが標準治療です。
一方、閉経後は、卵巣ではなく、腎臓のすぐ上にある副腎皮質から分泌される男性ホルモン「アンドロゲン」からエストロゲンがつくられます。その過程で働くのが、脂肪組織などにある「アロマターゼ」ですが、その働きを阻害するアロマターゼ阻害薬を使うとエストロゲンがつくられず、がんの増殖が抑えられます。
閉経後の再発予防治療としては、5年間アロマターゼ阻害薬を服用するのが標準治療です。術前にこの薬を使った場合には、術後と合わせて5年間になるようにします。
タモキシフェンを2~5年間服用後に閉経した人は、2~5年間アロマターゼ阻害薬の服用を追加するとさらに再発が抑えられます。再発・転移した場合も、ホルモン感受性ありの人はホルモン療法やmTOR阻害薬のエベロリムスなどを用いた治療を続けます。
さらに進む個別化治療
ホルモン感受性ありで腋窩リンパ節転移があったときや増殖指標のKi67が高いときには、抗がん剤治療(HER2陽性の人は抗HER2薬を併用)後にホルモン療法を行うのが一般的です。しかし、抗がん剤治療を行うべきか、専門家の間でも意見が分かれるのが、ホルモン感受性ありで再発リスクが中程度(グレード2、Ki67中程度、リンパ節転移なし)の人です。
このような人のがん細胞の中にある21の遺伝子を調べ、再発リスクと抗がん剤の効き目を調べるのが「オンコタイプDX検査」です。保険の対象ではなく検査料は自費(約40万~50万円)になるので希望者のみですが、抗がん剤の効果があるかどうかが事前にわかるので、無駄な治療をしなくて済みます。
開発中の検査法も含め、抗がん剤や分子標的薬の効果が得られる人が事前にわかるようになれば、乳がん治療はさらに個別化し、一人ひとり違ったものになるとみられています。
本コンテンツは認定NPO法人キャンサーネットジャパンが2018年10月に出版した「もっと知ってほしい 乳がんのこと」より抜粋・転記しております。